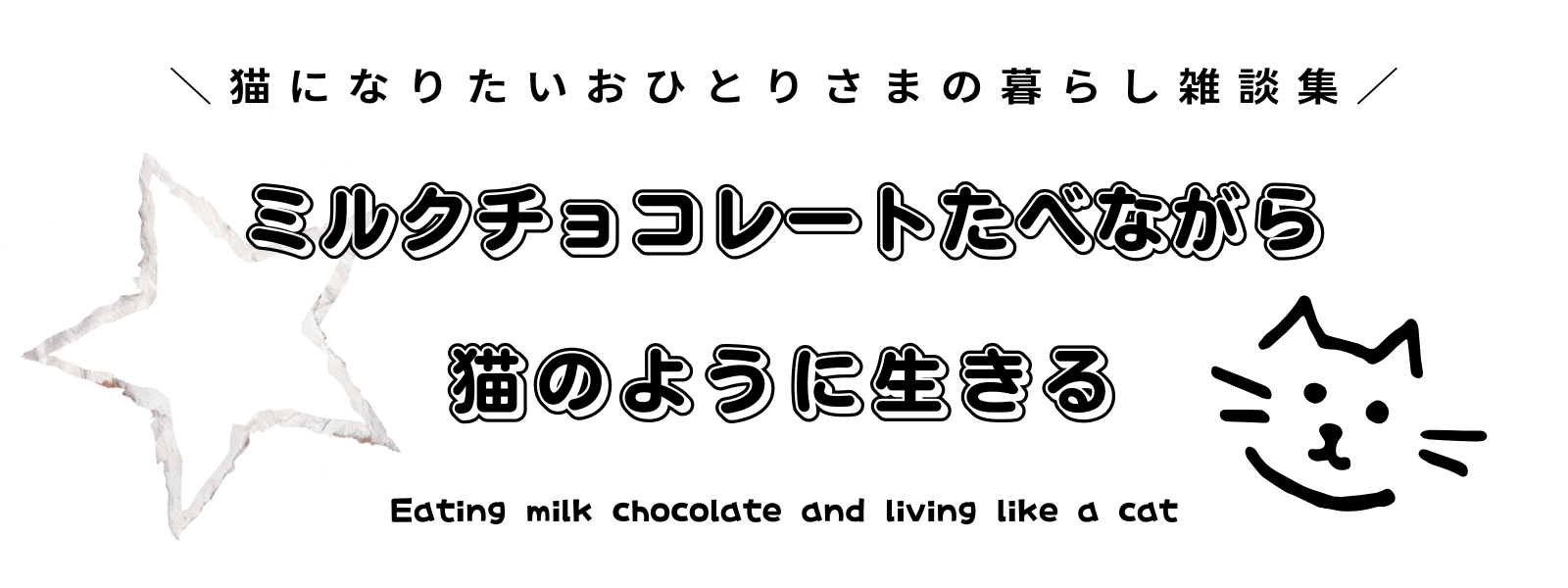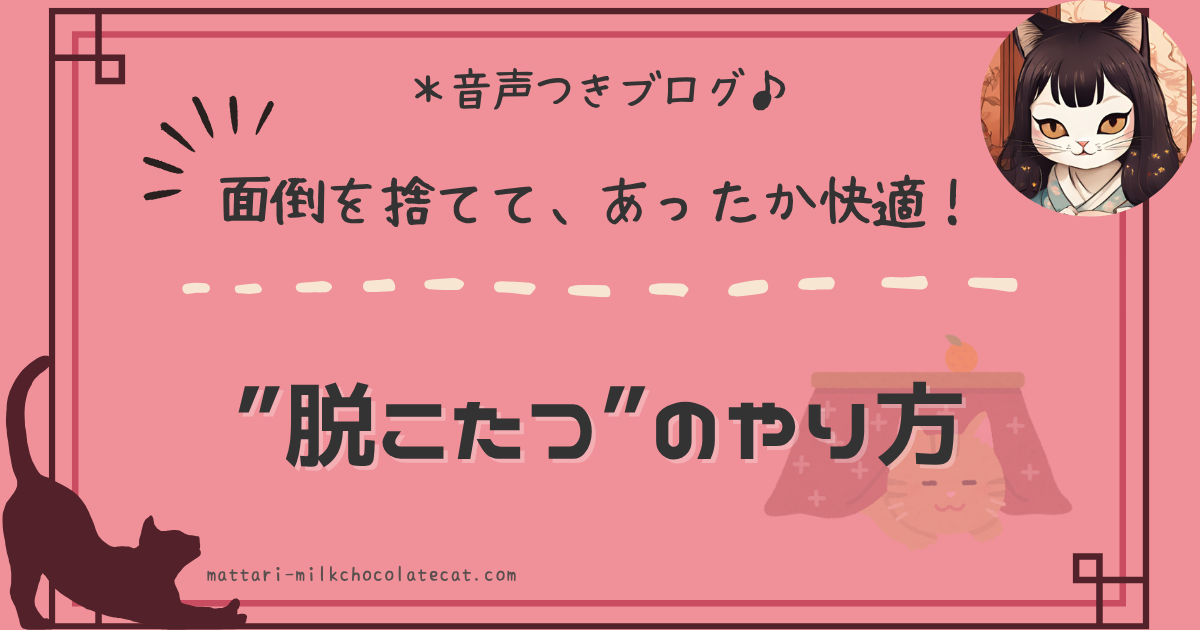はじめに
みなさんは「こたつ」好きですか?
冬の代名詞、ぬくぬくの幸福、そして—— 一度入ったら出られない魔力。
でも、片付けや保管を考えるとちょっとやっかいでもあります。
そこで思いました。
「こたつに頼らず過ごせないかな?」 と。
いきなり処分はしません。まずは置き換えの実験から。
この記事では、私が実際にやってみた“脱こたつ”のステップと代替アイテムをまとめます。
ポイントは、我慢ではなく“配置換え”。
からだ → 席 → 部屋の順で温めれば、意外といけます。
※本記事は、過去の「脱こたつ」連載4本を読みやすく再編集し、1つに統合した内容です。
【 この記事の要点 】
・からだ→席→部屋の順で温める(我慢ではなく“配置換え”)
・上:フリース/下:ボア+厚手靴下+レッグウォーマー
・必要に応じて電気ひざ掛けで即効&低ワット
| 部位/目的 | 最小セット | ポイント |
|---|---|---|
| 上半身 | ファーリーフリース+ハイネック | 脱着しやすいフルジップ/家で洗える/ゆったりサイズで空気層→保温UP |
| 下半身 | 内側ボアのスウェット+厚手靴下+レッグウォーマー | 足首の隙間ゼロ/裾は絞りタイプで“イン”しやすい |
| プラスα | 電気ひざ掛け/フリースひざ掛け/ネックウォーマー/手袋 | 局所温めで低ワット&即効/洗濯できるもの中心 |
| 生活導線 | 椅子・デスク運用へ移行 | 布類の管理から解放→“座ればすぐ暖かい席”を固定 |
こたつの「好き」と「困る」を仕分けする
好き:すぐ暖かい/安心感/ぬくぬくの幸福/猫の居場所。
困る:
- 動けない問題:座ったら最後、立ち上がりが重い
- 片付け問題:布団の出し入れ・干す手間・収納スペース
- 眠すぎ問題:心地よさに負けて作業が止まりがち
→ 結論:こたつの“あたたかさ”は残しつつ、運用だけ置き換える作戦に。
方針:からだ→席→部屋の順に温める(点→面)
いきなり部屋全体を暖めるより、「自分」→「作業席」→「部屋」の順がラクで早い。
第一歩は上半身の保温を固めることです。
上半身の装備|ファーリーフリースが最適解

- あたたかいのに軽い:家事・作業の邪魔にならない
- フルジップ:脱着しやすく、体温調整が秒でできる
- ハイネック:首元をふさぐと体感温度がグッと上がる
- 洗える&乾きやすい:日常メンテがラク
- サイズ感:ゆったりめで空気層を作ると保温力UP
使って良かったのは、家でガンガン洗えて乾燥までOK、多少ラフに扱っても平気なもの。
冬はとにかく着替えやすさ=続けやすさでした。
下半身の装備|“足首の隙間ゼロ”が合言葉
- ボア系スウェット:内側起毛。裾はリブ絞りだと空気が抜けにくい
- 厚手の靴下:できればウール等の動物繊維混で蒸れにくくあたたかい
- レッグウォーマー:ひざ下〜足首をカバー。パンツの裾をインして“隙間ゼロ”に
座り作業だとふくらはぎ〜足首が特に冷える。ここを覆えるかが体感の分かれ目でした。
プラスαの付属品|局所温め×ピンポイントで即効
- フリースひざ掛け/大判ブランケット:腰〜太ももを覆うだけで体感+1〜2℃
- 電気ひざ掛け:手足の冷えに直撃。低ワット&オフタイマーが安心
- ネックウォーマー:首・うなじを塞ぐと一気に温まる(ハイネックと重ねると効果大)
- 指なし手袋:キーボード作業向き。手首まで覆えるタイプが◎
- 室内ブーツ/モコモコスリッパ:足首まで包むと冷え戻りしにくい
“「身につける保温」+「必要なときだけ電源オン」”の二段構えにすると、からだが冷えにくく、続けやすいです。
部屋の工夫(最低限/私が実際にやっていること)
- エアコンの風向きは下向き。足元に暖気が回るよう固定。座り作業の体感が上がります。
- 風量は自動運転。ムダに強風を出さず、効率面でも◎。
- デスク常備:ブランケット/電気ひざ掛け。座った瞬間に暖かい=準備ゼロで始められるのが続くコツでした。
※加湿器は未所持。乾燥が気になる日は洗濯物の室内干しや電気ひざ掛けなどの局所暖房でしのぎます(安全には注意)。
3ステップで進める“脱こたつ計画”
Step1|準備(週末に1回)
- 上下の装備をそろえる(フリース/ボア系パンツ/厚手靴下/レッグウォーマー)
- ひざ掛け・ネックウォーマーを席に常備
- 可能なら電気ひざ掛けを設置
Step2|置き換え(2週間)
- 平日夜に30〜60分だけ“こたつオフ”で過ごす
- 座る場所をこたつ → 作業席へ
Step3|定着(+2週間)
- 週末のうちどちらか半日を“こたつ無し”に
- 物足りなければスポット暖房(パネルヒーター等)を足す
ミニチェックリスト
- □ 上半身:フリース/ハイネック
- □ 下半身:ボア系パンツ/厚手靴下/レッグウォーマー
- □ 席:ひざ掛け常備/必要なら電気ひざ掛け
- □ 平日夜:30〜60分“こたつオフ”達成
よくあるつまずきと対処
- 足先だけ冷える
室内ブーツ+レッグウォーマーで二重に覆う。パンツの裾は中にインして隙間ゼロに。必要なら電気ひざ掛けを足元へ(低ワットで即効)。 - エアコンの乾燥がつらい
できるだけ使用を控え、使うときは風向きは下向き・風量は自動で運転。加湿器は持っていないので、代わりに室内干しで加湿を補っています。身体を温めたいだけなら電気ひざ掛けなどの局所暖房も◎(安全には注意)。
まとめ|“我慢”じゃなくて“配置換え”
部屋の心地よさはそのまま、面倒な片付け・保管・日々の出し入れを手放せたら——冬がぐっと軽くなりました。
やったことはシンプル。
からだを先に温める(上:フリース/下:ボア+靴下+レッグウォーマー)、席にブランケットや電気ひざ掛けを常備、そしてエアコンは風向き下向き・風量自動。
これだけで、座ればすぐ温かい状態が作れます。
結果、
- 布団を干す“ヨイショ”がなくなる(管理がラク)
- 収納スペースを圧迫しない(片付けが短縮)
- 準備ゼロで暖が取れる(毎日がスムーズ)
(こたつテーブルはメルカリで手放し、こたつ布団は親戚の家へ。かさばる物が減って気持ちも軽くなりました。)
こたつを“手放す”というより、あたため方の配置換え。
今年の冬は、あったかさはそのまま/管理だけ軽く、でいきましょう。
※使って良かったアイテムは下の早見表にまとめています。
| 用途 | アイテム | 選び方・ポイント |
|---|---|---|
| 上半身 | ファーリーフリース/ハイネック | フルジップで体温調整◎/ゆったり目サイズで空気層→保温UP/家で洗えて乾きやすい |
| 下半身 | ボア系スウェット+厚手靴下+レッグウォーマー | 裾はリブ絞りで“隙間ゼロ”/靴下はウール混など動物繊維であたたかく蒸れにくい |
| 局所温め | 電気ひざ掛け(低ワット) | オフタイマー付きが安心/必要なときだけ電源オンで即効&省エネ |
| 座り作業 | ブランケット(大判) | 腰~太ももを広くカバー/毛足は短~中で扱いやすい |
| 足元対策 | 室内ブーツ/もこもこスリッパ | 足首まで覆える丈/脱ぎ履きしやすい形で“冷え戻り”防止 |
| エアコン運用 | 風向き=下向き/風量=自動 | 足元へ暖気を回す/ムダ風を抑えて効率◎/乾燥が強い日は室内干しで補助 |
※安全面(やけど・低温火傷)には十分ご注意ください。
\ぬくぬくを手放しぬくぬくを手に入れる/
では、またね (ฅ’ω’ฅ) ★
⭐音声で楽しむブログ
📢 この記事は NotebookLM(Google の要約・解説AI)で音声化しています。
読むより“ながら聞き”派にもどうぞ。(再生時間:約14分)
※内容確認していますが、音声と本文が異なる場合は本文が正式です。
※NotebookLMの概要は公式紹介ページをご参照ください。 → 公式紹介ページ
👇読んだよボタン♥️ポチッとしてもらえると励みになります♪